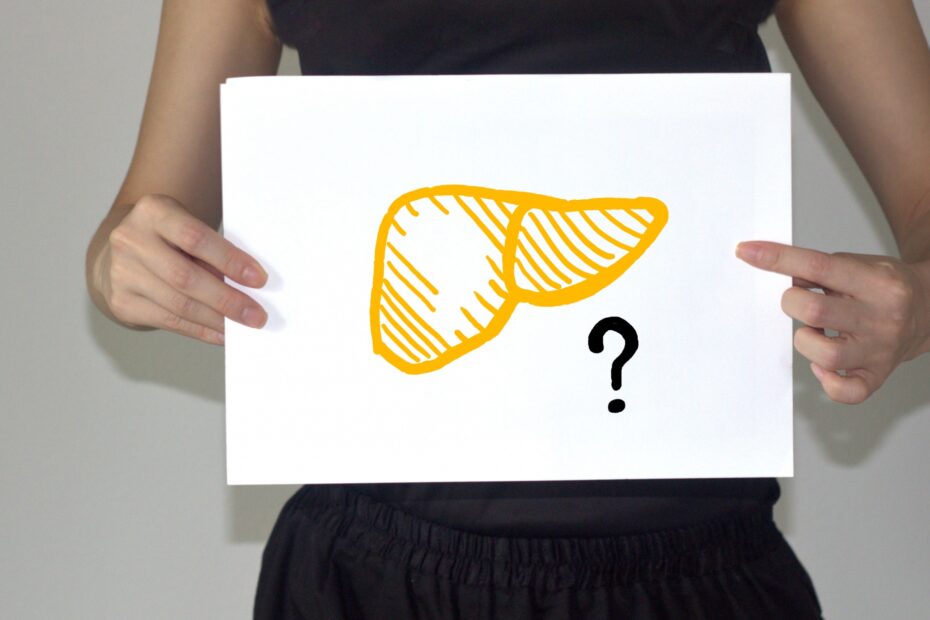第1章:アルコール性脂肪肝とは何か
脂肪肝は肝細胞内に中性脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。特にアルコール性脂肪肝は、長期間の飲酒により肝臓がアルコール分解を優先し、脂質代謝が後回しになることで発症します。アルコールは肝臓でアセトアルデヒドに代謝され、この過程でNADHが過剰に生成されます。NADHの増加は脂肪酸酸化を抑制し、中性脂肪の合成を促進するため、肝細胞内に脂肪が蓄積します。
初期段階では自覚症状がほとんどなく、禁酒や生活習慣改善で可逆的に回復しますが、進行するとアルコール性肝炎や肝硬変へと悪化するリスクがあります。そのため、体重減少だけでなく「肝臓代謝の正常化」を目指すアプローチが必須です。
第2章:脂肪肝の人に危険なNGダイエット
肝機能が低下している状態では、健康な人が行う一般的なダイエットが逆効果になることがあります。
1. 極端な糖質制限
糖質を極端に減らすと、肝臓はグリコーゲン不足に陥り、エネルギー産生のために脂肪酸分解が過剰に進みます。この際、ケトン体や遊離脂肪酸が増加し、肝臓への負担が増します。
2. 高たんぱく・高サプリ型ダイエット
プロテインやアミノ酸サプリを過剰摂取すると、尿素回路への負担が大きくなり、アンモニアが血中に蓄積する危険があります。
3. 急激な減量
短期間で体脂肪を大量に分解すると、血中の遊離脂肪酸が急増し、それが肝臓に再蓄積される「脂肪の出戻り現象」が起こります。
4. 長時間の高強度有酸素運動
乳酸やアンモニアの産生が増え、解毒・代謝処理が追いつかず疲労や倦怠感が強まります。
第3章:脂肪肝改善に効果的なダイエット原則
脂肪肝の改善には「肝臓への負担軽減」と「インスリン感受性の改善」が鍵です。
1. 適度な有酸素運動
ウォーキングや軽いジョギングを週3〜4回、1回30〜40分。中強度(最大心拍数の60〜70%)が理想で、脂肪酸の利用促進と肝脂肪減少が期待できます。
2. 筋トレで筋量維持
週2回程度、自重トレーニング(スクワット、プランク、腕立て)を行い、基礎代謝低下を防ぎます。筋肉は糖の主要な貯蔵庫であり、インスリン抵抗性改善にも有効です。
3. 栄養バランスの最適化
糖質は完全にカットせず、玄米や雑穀米など低GI食品を選びます。たんぱく質は1日体重1kgあたり0.8〜1.0gを目安に、魚・鶏・大豆食品から摂取。脂質はオメガ3系脂肪酸(青魚、亜麻仁油)を適度に取り入れます。
第4章:肝臓をサポートする栄養素と食品
脂肪肝改善には、肝細胞の修復や代謝を助ける栄養素を意識しましょう。
- オルニチン(しじみ、あさり)
→ 尿素回路を助け、アンモニアの解毒を促進。 - タウリン(イカ、タコ、貝類)
→ 胆汁酸の分泌を促し、脂肪消化とコレステロール代謝を改善。 - ビタミンE(アーモンド、ひまわり油)
→ 抗酸化作用で肝細胞を酸化ストレスから守る。 - ビタミンC(赤パプリカ、キウイ)
→ コラーゲン生成と抗酸化作用で肝機能をサポート。 - 食物繊維(海藻、きのこ、野菜)
→ 腸内環境改善により、肝臓への負担物質を減らす。
第5章:まとめと実践ステップ
脂肪肝の人は「痩せること」が目的ではなく、「肝臓を回復させること」が先決です。
- アルコールは完全休止:数週間〜数か月で肝脂肪は顕著に減少します。
- 極端な食事制限は避け、バランス重視:糖質は適量、たんぱく質は過剰摂取しない。
- 中強度運動+軽め筋トレ:脂肪酸利用と筋量維持を同時に行う。
- 肝臓サポート栄養素を積極的に摂る:特にオルニチン・タウリン・抗酸化ビタミン。
- 体重は月1〜2kgペースで減らす:急激な減量は脂肪肝を悪化させる。
この方針で取り組めば、肝機能数値(AST、ALT、γ-GTP)の改善が期待でき、健康的な体重減少とともに再発予防も可能になります。